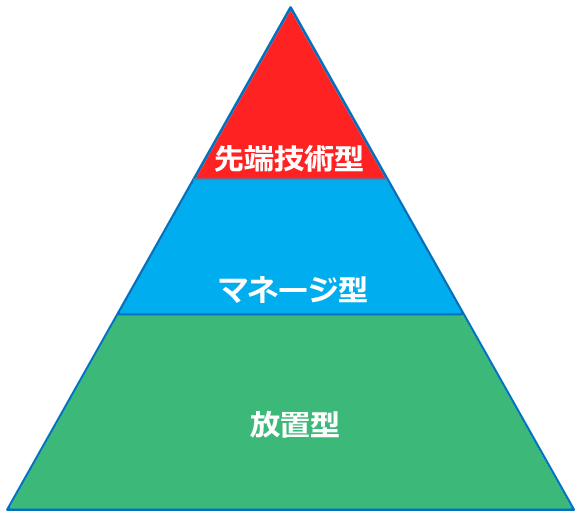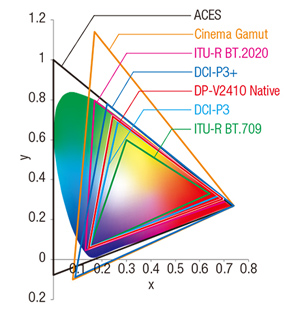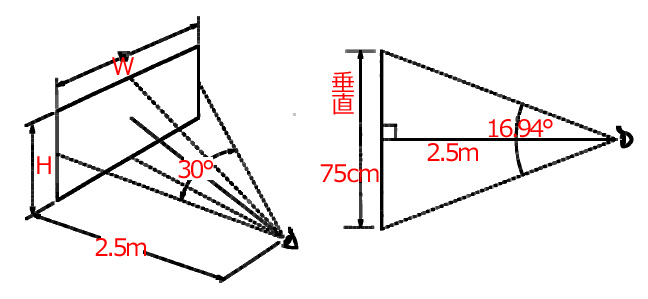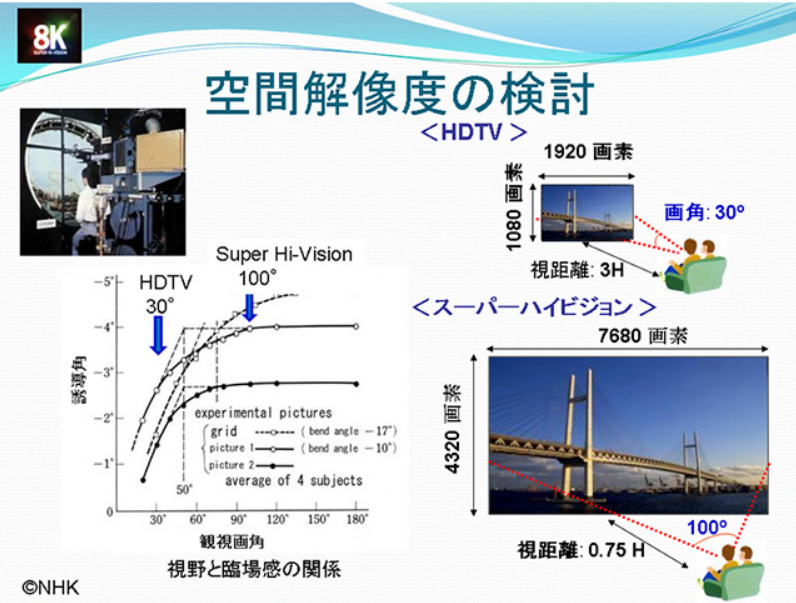2018.10.24
こんなところにサイネージがあったら...
こんなところにサイネージがあったら、有効に使ってもらえるのに、と思うことはよくあるが、たいていは先方に予算がない。パソコンでコンテンツを作るデジタルサイネージなら、予算はなくとも自分たちでコツコツとコンテンツを溜めていくことは可能かもしれないが、そういう動機づけをするには忙しすぎるとか人事労務上の制約が大きい。もし責任者が自分でヤル気を出せばやれないことはないのだが。
例えば私の住んでいるところにも小さな規模の保育園が増えていて、マンション立ち並んでいるところでは、1区画に一つくらいは設置されるようになった。だいたいは閉鎖した商店の跡地だったりして十分な広さや設備はない。保育士さんの人手も足りないだろう。こういうたくさんある保育園はだいたいは同じ時間帯に同じことをしている。ならば共通の保育番組を作ってネット配信すれば、個別にコンテンツを作らなくても使える。サーバーで保育園のID管理をしていれば、地域情報や自治体からの連絡などの個別の情報も入れられ、保育士さんの助けになるような使い方もできるだろう。

予算がないなら広告モデルでサイネージを提供したらどうかという考えもあるが、場所によっては広告は嫌われるし、また財布を持っていない保育園児を相手に何を売りつけるのか疑問である。これが美容院とか単価の高いサービスなら関連した商品も多くあるわけだから、広告モデルには向き不向きがある。もし広告モデルが可能でも、それをベースにコンテンツ提供を行っていくのは不安定で長続きしないということで、先方から信用されないかもしれない。
保育園向けのコンテンツとは、子供の遊びに関するものと、交通ルールや朝昼晩の生活全般に関して楽しく教えるものがある。すでに幼児本はいくらでもあるので、サイネージのコンテンツも自作しようと思えばできるはずだ。でも幼児本に専門の出版社があるように、子育てに何らかのビジョンをもって一貫したコンテンツ提供ができるバックボーンも必要である。
マルチメディアが登場してもう30-40年になるが、紙の出版社がデジタルメディアを提供するとか、出版社と連携してデジタルメディアを制作することは大変困難だった。その第一は収入モデルが違うからで、デジタルコンテンツのほとんどは書籍のようにまとまった収入にはならず、小銭がチャリンチャリンとなるので、これでは投資の回収の目途がたたないと判断されてしまう。
コンテンツビジネスでは紙からネットに移行したモデルは、情報誌、地図、レシピ、など多くあり、これからもどんどん移行は進むだろう。デジタルサイネージもそれに合わせて新たな利用分野が生まれてくることになろう。